|
日本病理学会員各位 東京大学人体病理学・病理診断学分野の深山正久です. これまでの活動と立候補の経緯私が病理学会と関わりをもつようになって24年がたちました.学会を組織として意識するようになったのは,1990年初頭,日本病理医協会の関東支部を立ち上げる際,当時の支部長下里先生のお手伝いをしたのがきっかけでした.1995年には独自の専門医制度の設立を目論む外科病理学会設立の動きがあり,これに反対する提起を行いました.その後,病理学会の法人化にあわせて,診断病理医部会を作る過程で診断体制委員として努力いたしました.また,その後も認定試験委員長,認定試験出題委員など病理学会員として活動してまいりました. 1999年に東京大学に移ってからは,人体病理学分野教授として,大学における人体病理学の在り方を追求してきました.先端的研究を展開する分子病理学のユニットに対し,生検診断,剖検診断に責任をもつ臨床的な病理学のユニットを作るために努力しました.この臨床的な病理学は,病院病理部に1対1に対応するユニットで,臓器病理の専門家数人以上を擁し,若い病理医育成に力を注げるシステム作りを目指したものです.これは東大の試みとして,病理学教室の一つのモデルを提供したものと自負しています.現在,病理診断の迅速化,またトランスレーショナルリサーチのための病理検体利用の整備,そして病理学の研究・教育に取り組んでいます. この間,病理学会の活動が支えになり,各種委員会の報告などに非常に啓発を受けました.学会活動の重要性を認識し,積極的に自分自身がそれを担うべき時期に来たと考え,病理学会の理事に立候補することを決意した次第です.病理学をどう捉えているかかつて,病理学は臨床医学の基盤をなす総合的,哲学的学問であり,病理診断は職人芸,名人芸でした.しかし,現在,病理学も医学,医療の中で大きく意義を変えています.病因を分子のレベルで解明し,病態を時間,空間の中に捉える「分子病理学」,標準的病理診断を安全,迅速に提供する「病理診断学」,医療に関連した死を解析し正しく医療にフィードバックする「剖検病理学」など,多面的な役割が要求されるようになっている,と考えています. 今後,日本の医学,医療に貢献するものとして病理学をどう変えていくのか,私たちはいま新たな変化,創造の時を迎えています.病理学会の活動に対する基本姿勢私は,病理学会活動の基本は,まず「人づくり」にあると考えます.病理学を現在担っている病理専門医,評議員の方たちは言うまでもなく,これから病理専門医や病理学を志す人たちが,いきいきと活動することが基本です.病理医の生涯教育,リクルートのためには地方支部の活動を重視したいと思います.これまで以上に,地方支部への財政的援助を行い,会員の自発的,創意にあふれた取り組みを推進すべきであると考えます.そして,これらの経験を交流する場が学術集会であり,また,会報であると思います. 当然,学術集会については,その会を主催する会長,世話人の自由度を高め,意欲,工夫をいかす体制にしたいと考えます.また,形態学に基盤をおいた研究活動の一層の発展をはかり,他学会の研究者との交流を深める試みを重視したいと思います. 次に,学会の社会的使命を果たすため,必要とされる課題に対しては,学会として迅速に対応し,国民の理解を得るべきであると思います.この点で,これまでの病理学会が果たした「病理検体の取り扱い」に関する先進的な役割,病理医不足に関する広報活動,医療関連死に関する取り組みを継承し発展させていかなければならないと思います.さらに,病理診断の重要性に関する広報,保険診療報酬での正当な評価をかちとるよう努力する必要があります. また,現在の病理学会の会費は,他学会に比較し高額となっています.病理学の果たす広範な役割を考えた場合,決して高いものではないかもしれません.しかし,この点はもっと現実的に検討しなおす必要があります.このため,学会各種委員会の機構を集約的に改編し,また,学術評議員システム自体も再考すべき時が来ていると思われます.先進的であり,民主的であること私は病理学会の執行部は積極的にアクションプランを示し,十分に会員に知らせ,議論を深めるように努力すべきだと思います.そのためにも,支部の活動は重要であると信じています.以上,病理学会ホームページ上の所信表明では,字数制限上,述べることができなかった点についても触れました. 私の考えに必ずしも賛成ではない方もいらっしゃると思います.私は十分に議論を尽くしたいと思います.このような熱意を信頼していただき,是非,私への投票をお願い申し上げます. e-mail: |
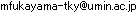 ,電話 03-5841-3344,FAX 03-3815-8379
,電話 03-5841-3344,FAX 03-3815-8379